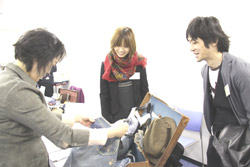12月初旬に開かれた日本最大の環境展示会「エコプロダクツ」は、エコに対する関心の高さを反映するかのように、多くの人が訪れていました。10年前に開かれた初回は、展示スペースも現在の半分ぐらいしかなく、ゴミ処理や環境汚染を防止する機器の展示会のようでした。来場者数をみても、そのときは5万人弱でも多いと思ったほどでしたが、それが20万人に迫るほどに膨れ上がっています。 そうした今回、ファッション業界に身をおく一人として注目したのがオンワード樫山のブースでした。以前から多くの消費財を扱う企業の出展が増えているのに、ファッション系企業が少ないのはどうしたものか、と思っていただけに、期待を膨らませて同社のブースを視察しました。結論から言うと、これはジャパン・クリエーションにも当てはまることですが、展示会では新たな発見や教わることが多い。そんなことを再認識させられるブースでした。 まず、「オンワード・グリーン・キャンペーン」では、販売したアパレル品を引き取り、東南アジアにリユースする一方、半毛加工によって製品化された軍手や毛布を難民支援しています。「環境配慮型ユニフォーム」はケミカルリサイクルによって循環化、水質汚染を防ぐ家庭で水洗いできる「ギガウォッシャブルスーツ」、このほか生分解するスーツや森林再生活動(高知県)への参加、ISO14001の認証取得、低公害車の導入…などなど、こんなにも環境対策がほどこされていたのか、と驚くほどでした。 これまで何度も記してきましたが、日本で家庭から捨てられる“アパレル・ゴミ”のうち3R、つまりリサイクルされている量は13%に過ぎません。そのうえ温暖化防止にも対応していかなければなりません。それだけにファッション産業でリーディング企業となる同社がエコプロダクツに出展した意義は大きいといえます。 |
これまでファッション業界では、ややマイナーな存在とみられてきた古着やお直しの店がクローズアップされています。この秋、東京・新宿にリニューアル・オープンした丸井アネックスに「RAG TAG」と「ペーパーメイクオーバー」が出店したのをはじめ、東京・青山には「アルターイン」というリメイクショップがオープンしています。 RAG TAGは、すでに年商が50億円を越える(株)ティンパンアレイが運営しているユーズド・セレクトショップでラグジュアリー系やストリート系、モード系、キャリア系など1000ブランド、3000ものアイテムがラインアップ。一方のペーパーメイクオーバー(社名同じ)はリメイクを専門にするショップで、ここでは両親が着ていた服を子供用にリメイクするサービスを行なっています。また、アルターインはサイズなどの補正・修理を主力にする(株)ツヅキが打ち出した新業態で、一見するとレストランのような外観の洒落た店となっています。 こうしたユーズドやリメイクの店が、ファッションの世界で“一等地”と呼ばれるところに出店する背景には、やはりエコとの関連が見逃せません。百貨店が不用品の下取りをするように、新品を扱う小売業にとってもエコはトレンドの一つかもしれません。 しかし、これら3社に共通しているのは、単にエコというトレンドではなく、「古着に新しい価値を付けて生まれ変わらせる」(ティンパンアレイ)、「思い出のつまった服を、愛する我が子の洋服に仕立てる」(ペーパーメイクオーバー)というマインドにあります。 そこで思い浮かぶのが“MOTTAINAI”というフレーズです。「勿体無い」という日本語を、ケニア出身の環境保護活動家でノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイさんが世界に広めたことで知られていますが、この“MOTTAINAI”がユーズドやリメイクの底流になっていることも確かなようです。ちなみに、マータイさんが語ったところによると、英語の「wasteful」(不経済な、もったいない)ではリデュース、リユース、リサイクル、リスペクト(尊敬)の概念が表現できず、日本語の「勿体無い」にはすべてが包含されている、というのです。 |
先日、東京・神田で開かれたユーズド・ファッションのエクスチェンジ(交換会)に参加しました。クローゼットに休眠中のファッションを持ち寄り、気に入ってもらえばタダで引き取ってもらう、いわばフリーマーケットの無料版といえば分かりやすいかもしれません。こうしたイベントがあることは知っていましたが、参加するのは今回が初めてでした。 前日に持ち込む服を選んでいると、あるものですね“不良在庫”は…。その多くはサイズの不適合品で、痩せる努力もしないのに「いつか着られる日が来るのでは…」と捨てられない服がダントツのトップ。次が流行遅れになったもので、海外旅行の土産に買ったガウンとも久しぶりに対面しました。 とりあえず、誰かに着てもらえることを念じて3点を持参したのですが、捨ててもいいと思っていた“服たち”なのに、会場に行くと貰い手が見つかるかどうかの不安が。そして、その心配は見事に的中しました。オープンして4時間も経つのに、持参品はハンガーに架かったままなのです。 もともと無料の交換会ですから、値段を下げるわけにもいかないし、最悪のときは持ち帰えるしかない。遠くから出来の悪い子供を参観する親のような心境で服たちを見守っていると、事態は好転。何と完売ならぬ“完贈”したのです。思わず新たなオーナーに駆け寄り、感激の握手を求めてしまいました。 いつの間にか溜まってしまった不用の服たちにも、感情が移入していることを実感する1日でした。 |
先日、「エコランド」に行ってきました。こういうと遊園地を連想されるかもしれませんが、着いた先は物流センターでした。外見はよくある物流センターで、どこに「ランド」があるのか…。案内された施設は、まるでゴミの山のようで、古ぼけた冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、インテリア、廃材のスチール、衣服、コンクリートのブロックまでありました。 ここは物流企業のウィンローダが2004年から始めたエコ事業の拠点で、すべてが家庭から引き取った不用品の数々です。これをリサイクルしているのが「エコランド」でした。ここが取り組んでいるサービスは、エコ回収という片づけ・回収・買取り、次がエコオク、リサイクルショップなどのリユース、そしてリサイクルに、リアライズと呼ばれる工房などで構成されています。 簡単に説明すると、同社に不用品を引き取ってもらうと、再利用できるものはインタへネットのオークション(エコオク)や直営のリサイクルショップで販売されます。リユースできないものはリサイクル処理されますが、これら不用品にデザインを加えて再生しよう、というのが「リアライズ」というプロジェクトです。 古タイヤとシートベルトでつくったスツール(写真)や、椅子を分解したテーブルなど、デザイナー参加によるこのプロジェクトでは、さまざまな製品が生まれています。 そして、こうした一連の活動が認められ、同社は「2009年グッドデザイン賞」を受賞しました。 http://www.eco-kaisyu.jp/ |
「このプラスチックの匂いを嗅いでみませんか?」−先日のJFWジャパン・クリエーションでブースを回っているときのことです。島精機製作所の会場に併設された(株)ヤマトクリエーション和歌山のコーナーには、一見すると木材のようなパーツが展示されており、この“木片”に鼻をあてると梅の香りがするのです。聞けば島精機が拠点にする和歌山の名産品である梅の種を原料にしたバイオマス・プラスチックなのだそうです。マネキンの大手であるヤマトマネキンでは、バイオマス・マネキンの開発に取り組んでおり、この“梅の香り”もその一つでした。 動植物から生まれた再生できる有機性資源を「バイオマス」といいますが、最近はバイオエタノールやバイオディーゼルなどエネルギーが話題になっていますが、木質プラスチックや生分解性プラスチックの開発も進んでいます。残材やオガ粉などの原料をプラスチックに混ぜてバイオマス・プラスチックをつくるわけですが、その原料は間伐材をはじめ放置林原木、加工残材、食品加工残材…などなど、いわゆる放置しておけばゴミになるものばかりです。 この資源活用だけでなく、このバイオマス・プラスチックはCO2の排出抑制にも効果があるそうで、国内で生産されている石油由来プラスチック1400万トンを、すべてバイオマス由来に転換すると最大4400万トンのCO2削減につながるといいます。 まだ大量には出回ってはいないようですが、売り場のマネキンをじっくり観察してみるのもいいかもしれません。ただし、すべてのバイオマス・マネキンが香りを発するとはかぎりませんから、マネキンに鼻を当てる行為は自粛されたほうがいいかもしれません。 |
先ごろ開かれた「ジャパン・クリエーション2010A/W」では、エコに関連したブースが目立ちましたが、なかでも注目されたのが「JEANISM JAPAN QUALITY」をテーマにした日本ジーンズ協議会のブースでした。 |
先日、東京と大阪で「リサイクルの新しい動きが始まった」と題するセミナーが開かれました。中小企業基盤整備機構が主催したもので、東京会場に行くと空席を捜すのに苦労するほどの盛況ぶり。これは繊維ファッション業界でも、まちがいなく環境に寄せる関心が高くなっていることを裏付ける光景といえます。 |
あらためてアメリカは“慈善先進国”という思いを強くさせられる話です。日本では家庭から捨てられるアパレル・ゴミの3R率は10%台が続いていますが、アメリカでは10年前から30%を越える水準となっています。その要因の多くが教会などを通じての慈善活動だといわれています。エコというより人々の慈善意識が、古着のリユースを活発にしているようです。 その大型プロジェクトが、以前にもこのコラムで紹介しました「NY GREEN FASHION」(http://www.nygreenfashion.com/)が伝えています。それによると全米に1065店舗をもつメンズ専門店のメンズウエアハウスは、不要となったスーツを回収し、これを経済的に恵まれない人たちに、リクルート用に寄付するキャンペーンを行なっています。同社は昨年も同キャンペーンを実施しており、そのときは2か月間で12万アイテム(うちスーツは3万5000着)を回収、この回収したスーツに同社は新品のドレスシャツをつけて120の非営利団体を通じて寄付しています。 今年は9月の1か月間だけで15万アイテムの回収を計画しており、この中からリユースされるスーツには新品のネクタイを添えて寄付するそうです。以前から同社は、リクルート・スーツが買えない人々に、日本円で数億円の新品スーツを寄付してきましたが、これでは間に合わないとして、古着の回収に乗り出しました。ちなみに回収するアイテムは、スーツをはじめドレスシャツ、ネクタイ、ベルト、靴で、「あまり着ていない、きれいな服」と呼びかけているようです。 |
それがエコによるものなのか、ファッション性によるものなのかは分かりませんが、若い世代に古着派が増えているのは確かなようです。「古着派」というより新品と古着を、ボーダレスの価値観で使い分ける、といったほうが正確かもしれません。そのぐらい古着を身に着ける若者が増えています。 そのことを裏づけているのが、岡山県で行なった「リサイクルショップ(古着屋)に関する調査」です。これは「タウン情報おかやま」のメール会員450人を対象にしたもので、それによると58%の人が「リサイクルショップでの購入経験がある」と回答しています。 ところで、この調査では購入経験だけでなく、リサイクルショップに売ったことがあるかどうかも質問していますが、「売り買いの経験あり」と答えたのは31%で、ここでは世代格差は見当たりませんでしたが、今後の意向を聞くと「売りたいし買いたい」が57%に跳ね上がり、ここでは20〜30代とともに40代が60%を占めました。 やや古い調査になりますが、経済企画庁(現内閣府)が2000年に行なった「リサイクルショップの利用に関する意識調査」でも「リサイクル衣料として売ってみたいか」の問いに6割の人が「売ってみたい」と答えています。そこで興味深いのは“販売価格”で、この調査によると「ただでもいい」は16%でしかなく、「購入価格の1割くらい」が24%、「同3割くらい」が32%、「同7割くらい」が16%となっていました。 アパレル・リサイクル品の“セルシューマー(販売する消費者)”が6割、これが古着市場の拡大を予兆するデータとなるのかどうか…。 |
ちょうど1年前に、このメルマガで『古着がエネルギーになる』というコラムを載せましたが、アパレルの完全リサイクル化をめざした試みが、今月からスタートしました。経済産業省と中小企業基盤整備機構が支援する「繊維製品リサイクル・モデル事業」がそれで、このプロジェクトに参加したワールドと良品計画では、今月から使用済みアパレルの回収を行なっています。 【参加企業】 |
百貨店などでの不用品下取りが話題になるなど、ファッションの世界でもエコへの取組みが本格化しつつあるようですが、そうしたなか“エコの逆風”に耐えているのがネクタイではないでしょうか。クール・ビスによって男性のビジネス・ファッションは一変、昨今は「夏場はネクタイが無用…」と思えるほどノーネクタイが広がっています。 それだけに注目されるのが、(株)たまき(本社横浜http://www.tamac.co.jp/)という会社のエコ戦略です。ネクタイやリボンを主力にする同社は、7年前からネックウエアのリサイクルに取り組んでいます。帝人ファイバーとの協力によって、使用済みのネクタイやリボンを回収し、そこから得られたリサイクル糸で再びネクタイ・リボンを製造するといった、いわゆるケミカル・リサイクルを推進してきました。 これによって廃棄されるネクタイが軽減できるほか、CO2の発生も在来品に比べて30%も削減されるそうですが、この排出削減を100%にするため同社は、国連認証済みの排出権を用いたカーボンオフセットを採用することになりました。インドや韓国の風力並びに水力発電プロジェクトの排出枠を購入するもので、同社の製品を購入した客にはカーボンオフセット証明書が発行されます。これまで同社は業務用のネックウエアを中心に展開してきましたが、今後はリサイクルとエコを一般消費者にも訴え、さらに業容を広げていく計画です。 それにしてもファッション製品でCO2排出量を100%削減してしまう、というのはすごいことですね。 (※)カーボンオフセットとは、CO2等の温室効果ガスの排出について、排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても排出される温室効果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方です。(環境省) |
会場には30のブースが設けられ、リフォームをはじめカケハギや古着回収、ファイバー・リサイクルなど、さまざまなエコ関連企業が紹介されていましたが、会場を訪れた人にとっては、日ごろ目にすることが少ないリフォームやリメイクだけに、それぞれの技術が新鮮に映ったようです。 今回がはじめての同ワークショップは、運営の多くをボランティアが支え、社会人や学生など100人あまりが参加。同時進行で行なわれたセミナーも、ファッション・エッセイストのフランソワーズ・モレシャンさんをはじめ、講師のほとんどがボランティアによる講演となりました。 一般的なファッション・イベントにくらべると、出展者の数も少なく、手づくりのようなイベントでしたが、「いいものを長く大切に…」というリデュースに対する関心の高さを実感するとともに、ライフスタイルだけでなく、このリデュースが新たなビジネスモデルになる可能性を示唆するワークショップでした。 |
「広東省、使用禁止の発癌性の染料を含んだ衣料品を検出」…こんな見出しの記事がホームページに掲載されていました。これを伝えたのは福井県香港事務所で、「深セン特区報」が4月30日付で報じたところによると、広東省品質技術監督局が広州、仏山、深セン、東莞、中山の5都市の企業80社が生産する女性用アパレル製品の品質検査をしたところ、一部に使用が禁止されている“アゾ染料”が含まれていた、というのです。 この検査では女性用アパレル製品80ロットが対象となり、このうち合格したのは47ロットで、合格率は59%だったそうです。詳しい検査内容は明らかでありませんが、ここで不合格となった製品の中には、中国でも使用が禁止されているアゾ染料を用いたものがあり、それが冒頭の見出しになりました。 「アゾ染料」とは聞き慣れない言葉ですが、じつはアパレルだけでなく、印刷や化粧品、医療、食品など、数多くの分野に用いられており、その種類は3000にのぼり、化学染料の半分近くを占めるそうです。このうち“芳香族アミン”(特定アミン種)を生成するアゾ染料に発癌性があるとされ、1994年にドイツで20種類の発ガン性アミンを生成するアゾ染料の使用が禁止されたのをはじめ、現在では多くの国が生産を禁止したり、規制したりしています。 そうした中での検査結果だけに、中国製のアパレルが大半を占める日本としては、他人事ではありません。先の深セン特区報では『アゾ染料を使用している衣料品は、外観だけでは識別できないが、一般的に色が鮮やかな衣料品に使用されている可能性が高く、専門家は服を購入する際は、有名ブランドの商品で、できれば淡い色の服を選ぶのが好ましいと呼び掛けている』と報じていますが、この説だけで納得する日本人は少ないはず。ヨーロッパでは、基準を設けて合格した製品にマークを付ける動きがあるようですが、日本の対応が気になるところです。 |
あまりの変わりように感涙する依頼者…テレビ朝日系列で放送している「ビフォーアフター」が、この春から復活しました。古くなった家を匠と呼ばれる大工や建築士がリフォームする番組なのですが、その変貌ぶりは依頼者だけでなく、視聴者にも感動を与えるほどの出来栄えです。 この番組は2002年に放送が始まり、3年間のブランクを経て4月から“Season II”として再スタートしました。これまでに登場した匠は100人近くに達し、ここでリフォームされた家は140軒を超えるそうです。 わがファッション業界でも「創・匠・商」が叫ばれ、クリエーションだけでなく、優れた技をもつ匠の必要性が再認識されていますが、“ファッションの匠”といわれると、思わず首を傾げてしまいます。確かに製織や染色・整理、図案などテキスタイルの世界には数多くの匠が存在しますが、アパレルの世界ではパターンメーカーを除けば、その存在が埋没しているのが実情です。縫製の世界ではコストばかりが優先され、技術が話題になることは稀です。 そんななか、まさにファッション版の「ビフォーアフター」ともいえる匠がいました。東京の原宿や代官山でひそかなブームとなっているリメイクショップがそれで、ここでは古着がまるで新品のように蘇っています。リフォーム自体は、いまに始まったことではありませんが、ここで匠の技が発揮されるのは、ファッションセンスと応用力、そしてカットしたり縫い上げたりする技術力です。 そこで思うのは、こうしたリメークとファッション教育の関係です。まだ、リメークを専門に教える学校は少ないようですが、感性と技術が求められるリメーク教育は新製品開発にも生かせるはずで、エコの観点からみても時代に即したテーマだと思うのですが、どうでしょう。 |
このところファッションの世界でリサイクルが、ちょっとした話題をつくっています。「リサイクル」とはいわずに「トレード・イン」という言葉が使われていますが、いわゆるファッションの下取りがそれで、百貨店や量販店などが今年になって積極的に打ち出しています。下取りする品目や方法は店によって異なりますが、環境保護と集客アップのダブル効果が期待できるこの戦術が、“ファッション3R”に寄与することはまちがいありません。 これまで何度もこの欄で記しているように、ファッション、それもアパレルの3Rは決定打を欠いたままの状態が続いています。年間100万トンを越えるアパレル・ゴミが家庭から出されながら、3Rで処理される量は十数万トンに過ぎません。しかも「3R」といいながら「リユース」と「リサイクル」が大半を占め、「リデュース」への対応はごくわずか、というのが現状です。 リデュースとは「減少する」の意味で、3Rではゴミの発生を抑制することをさしています。モノのライフサイクルを長寿化することで、良いものを長く使い続けよう、という考え方です。かつては日本でも“洗い張り”で、キモノを解体しては作り直す習慣がありました。手編みのセーターでも、子供服のようにサイズが合わなくなると、ほどいて編み直すことが、つい最近までとはいいませんが、そんな光景が見られました。 そうしたなか、そのファッション・リデュースを盛り上げるイベントが、この夏、東京で開かれます。「リ・ファッション・ワークショップ2009〜ここから始まる、私たちのリ・ファッション生活」というイベントを開くのは日本リ・ファッション推進委員会です。ファッションのリデュースを広げる目的で設立されたばかりの委員会ですが、このイベントについては「(着なくなった服などを)匠の手仕事で変えられ、よみがえることの素晴らしさを知ってもらうために、生活者と供給者が集い、生活の中にリ・ファッションを広げていきたい」と説明しています。 当日は、リ・ファッションに関する基調講演のほか、ファッションと環境やユニバーサルにちなんだ講演や交流会が行なわれます。 開催日時 7月4日(土曜日)午前11時〜午後6時 |
先に開かれたJFW-JC2010S/Sでも話題になったように、「エコ」に対する世の中の関心は年を追うごとに高くなっています。なかでもオーガニック・コットン製品は驚くほどのピッチで市場を広げています。0rganic Exchange Marketplace Report2007によると、2001年に日本円で270億円だった市場規模が05年に640億円に拡大し、さらに07年になると2160億円に増加しています。さらに同レポートによれば2010年には7500億円くらいの規模になる、と予測され、この数字が達成されると、10年間で約30倍という伸び率になります。 とはいえ、オーガニック・コットン製品の全繊維に占める比率は小さく、仮に日本が世界の10%を占めるとしても、その市場規模は07年時点で200億円強にしかなりません。それでいながら生活者のオーガニック・コットンに寄せる関心は高く、大手シンクタンクの調べによると、日本人の6割がオーガニック・コットン製品を認知していて、4人に1人がオーガニック・コットン製品の購入経験がある、のだそうです。そして、この調査で注目されるのが、今後の購入マインドで、じつに53%の人が「購入したい」と回答しています。 購入経験に関しては女性のほうが多く、30代を除くと各世代で30%を越えています。ちなみ男性のほうを見ると、最も高いのが20〜30代の世代(22%)で、その他の世代は20%にいたっていないのが実情です。ところが、今後の購入に対する意識では、男女とも世代間の差異が見られず、男女とも2人に1人が「購入したい」とこたえています。 また、オーガニック・コットン製品に対するイメージでは「環境に優しい」が6割前後を占め、次いで多いのが「安心して身に付けられる」(58%)や「肌に優しい」(47%)などで、「栽培農家の健康被害が削減できる」は26%でした。 この調査では、あわせて業界専門家へのヒアリングも行なっていますが、「肌に優しい、アトピーが治るという宣伝は確かではない」という意見とともに、「(オーガニック・コットン製品は)地球に優しいという訴求が世界の常識」という見解が示されました。 ある専門家は「地球環境とともに、オーガニック・コットン製品は栽培農家の健康被害を減らす、というフェアトレードを促進させる効果があります」と話しています。 |
デニムの生地を高速織機で織り上げるためには、生地の両端を補強し、織り上がりのゆがみやよれを防ぐ必要があります。それが“耳”といわれる部分で、織り上げた後にはカットされて工場から出荷されます。日本のデニム業界では、この耳が1日約20万メートル、1年間で地球2周分近くが廃棄されているといわれます。 このデニムの耳を有効活用しようと、さまざまな分野で作品づくりが行なわれていますが、このほどファッション・ビジネス学会のアパレルリサイクル研究部会に所属する杉野服飾大学の先生が、デニムの耳を使ってドレスなど2点(写真)を製作しました。同大学准教授の田原美津子さんは白のビスチエとドレスを、また同大学講師の井口多恵子さんは耳を編んだトップスに挑みました。 白のビスチエとドレスでは、耳を何回も漂白してビスチエやドレスの模様に使っています。一方の編みこんだトップスは、耳を細く切り、幅の異なるテープ状にしたものを交互に編んでいったものです。ちなみに制作には1ヶ月近くかかったそうです。なお、作品についてのお問い合わせは下記の通りです。 iguchi@sugino.ac.jp |
先日開かれた「ジャパン・ベストニット・セレクション2009」の会場で、「おや…?」というブースに出会いました。東京・有楽町の東京国際フォーラムで開催された同セレクションは、匠のワザをもつニット製造業49社が出展する、文字通り“日本発”のニットウエアが一堂に会したものですが、その会場を取材していると『歩くぬか袋』というキャッチコピーが目に飛び込んできました。 履くだけで米ぬかパワー!かかとツルツル。足すべすべ……ブースの入口には米俵が置かれ、まるで食品見本市にでも来たような感じのブースなのです。最近、いろいろなメディアが「米ぬか美容法」をとりあげていますが、奈良の靴下メーカー、鈴木靴下は日本で初めて米ぬかを使って保温と保湿に効果がある製品を開発しました。 米ぬかは、玄米を白米に精米するときに出る、いわゆる米の皮ですが、この栄養価については、江戸時代から認められていました。それが「ぬか袋」で、入浴時に米ぬかを詰めた袋を入浴剤や石鹸のように使い、女性の美肌を保っていたそうです。 この効能に着目した同社は、和歌山県工業技術センターの指導を受け、築野食品工業とオーミケンシの協力を得て製品化に取組み、レーヨンと綿の混紡繊維である「米ぬか繊維SK」が生まれました。天然セルロースが原料のレーヨンは、繊維自体がスポンジ状になっており、断面に小さな穴が沢山あります。その穴の中に米ぬかの天然成分(γ-オリザノール)を練り込む、という技術です。ちなみにγ-オリザノールには抗酸化作用があって、活性酸素を取り除き、血流を良くする効果があります。 |
エコやCO2と並んで最近よく耳にする言葉にサスティナビリティ(sustainability)があります。その意味は「持続可能性」で、一般的には持続可能な環境や社会への考え方や取組みをさしていますが、ファッションの世界でも頻繁に使われるようになっています。その代表がオーガニック製品で、オーガニック・コットンの需要が急増していることは、以前に紹介したとおりです。 一方、製品のライフサイクルでもサスティナビリティが話題になっています。3R(リデュース、リユース、リサイクル)のうち、リデュース、いわゆる廃棄抑制に相当するもので、これまでの使い捨てをやめ、できるだけ長く使い続ける、というのも「持続可能性」になります。先日も朝日新聞でファッションのリペアが取り上げられ、セーターなどニットでの修理依頼が増えている、と報じていました。また、先日伺ったシューズメーカーでは、系列に修理工場を設けており、そこでも底の修理依頼が山積みになっていました。 そうしたなか、イギリスでは信じられない“リデュース”が生まれています。Howieというメーカーが「Hand-Me-Down」(http://www.howies.co.uk/)というブランドで「品質保証期間は購入後10年」という公約を打ち出したのです。ジャケットだと400ポンド(5万5千円弱)の価格帯ですが、それを10年も品質保証するというのです。 「私たちは限りある資源にもかかわらず、それらを消費する無制限な願望の時代に生きています。私たちは、私たちの消費に対する多くの責任を消費者とともに共有しなければなりません。ここでの重要な要素はグッド・クオリティとグッド・デザインです。この製品は購入時から最低10年間は保証されます。もちろんこれよりも長い期間、十分お使いただけます」(同社のHPから) これらは、ファッションにおいてもサスティナビリティが、さまざまな形で進行していることを物語っています。 |
このところ温室効果ガスの排出抑制に話題が集まり、ややトーンダウンしていた繊維リサイクル(3R)ですが、これへの取り組みが強化されることになりました。繊維3Rについては、これまでも本欄でとり上げてきましたが、中小企業基盤整備機構の調べによると、2004年に家庭などから廃棄された繊維製品は230万トンに達します。このうちリサイクルに再利用されている量は10万トン、古着などリユースされている量が23万トンで、合計197万トンが一般廃棄物として処理されています。これに加えて企業から捨てられる産業廃棄物が15万トンもありますから、年間210万トンもの繊維廃棄物が埋め立てや焼却で処理されていることになります。 これまでも繊維業界では、それぞれの業界ごとに3Rの取り組みが進められてきましたが、素材の複合度の高さや製品の多様性・ファッション性、さらには再生用途の難しさや複雑な生産・流通構造などの要因があって、なかなかリサイクル率が上がってきませんでした。もちろん、合繊のケミカル・リサイクルや生分解繊維の開発、コットンのエタノール化などの新技術が開発されていますが、全体を底上げするまでにはいたっていません。 そうしたなか、経済産業省では休止状態にある「繊維製品3R推進協議会」を再開し、繊維リサイクルを促進していくことになりました。産学官による同協議会では、各業界が策定したアクションプランのフォローアップをはかるほか、今後の繊維リサイクルの将来像を検討するというもので、具体的には繊維リサイクルの技術検証と廃繊維の回収モデル構築を目的にしたワーキンググループを新設し、リサイクルの効果を上げていく方針です。 技術面では古着のリメイクや繊維性状ごとの最適技術の検証などを、また回収面では店頭回収における課題整理(保管場所、店舗イメージ)やコスト、回収によるメリットなど、細かな課題を検証していくことになっています。 |
最近は景気ばかりに話題が集中し、やや関心が薄れてしまったように映る環境対策ですが、昨年から京都議定書に定められた温室効果ガス削減目標の第一約束期間に入りました。それは2012年までの5年間の排出量を1990年にくらべ6%削減するというもので、さまざまな業界で目標達成のための自主行動計画が発表されています。その骨子となるのがC02の削減で、これを環境省では「チーム・マイナス6%」と銘打って、企業だけでなく、国民一人ひとりが参加するよう呼びかけています。 とはいえ、いきなり「6%削減」といわれて即座に対応できる人は、そう多くないと思われます。節電ぐらいは思いつきますが、何をどのぐらい気をつければ6%にたどりつくのか…。そのあたりの参考事例をチーム・マイナス6%事務局(http://www.team-6.jp/)では、次のように算定しています。 1)暖房を20度、冷房を28度に設定すると0.6%減(1世帯あたり) 「一人ひとりの力はそれほど大きくないかもしれません。でもみんなの力がチームとなって結集すれば、地球規模の大きな力になれるのです。『チーム・マイナス6%』には、そんな思いが込められています。そして、その力は、確実に地球温暖化防止に役立つのです」 |
今回はリサイクル、それもアパレルのリサイクル輸出についての話です。繊維リサイクルでも3Rといってリデュース(発生抑制)、リユース(再利用)、リサイクル(循環)の3つが基本となりますが、このうちもっとも多いのがリユース、すなわち古着としての再利用です。最近、日本でも古着市場が希少なファッションを求める若者たちの人気を集めていますが、その多くは輸出が占めています。アパレルリサイクル率が70%といわれるドイツでも古着の輸出が主体となっています。 古着の輸出も行なう故繊維企業ナカノ(株)の窪田恭史さん(リサイクル部事業企画室長)によると、日本の古着輸出はいろいろな事情があって東南アジアに集中しているそうです。詳しくは窪田さんのブログ(http://blog.goo.ne.jp/hardworkisfun/c/706177760f0fcf04a972b7ebe9a26580=リサイクルの歴史)に記されているため、ここでは割愛しますが、そのブログで再認識したのが東南アジアにおける古着ニーズです。結論から言うと、これらの地域で求められるリサイクル品が、日本では集めにくいということです。 窪田さんによると、東南アジアでニーズが高いにもかかわらず、日本で放出されないアイテムは、ハンカチをはじめ女性用肌着、タオル、野球帽などの実用品です。日本人の価値観からいえば、どれも古着としての価値が低く、フリーマーケットでも新品しか見当たりません。しかし、そうした実用品が東南アジアでは求められています。そのあたりについて窪田さんは、このように述べています。 「中古衣料を必要としている多くの国の人々にとって、衣類はあくまで生命を守る必需品なのであり、ファッションを楽しむところまでいたっていません。わたしたちはともすると自分たちに価値のあるものは海外の人々にも喜ばれるものと思ってしまいがちですが、必ずしもそうとは言えないのです。繊維リサイクルの効率を高めるため、また海外の国々とのより良い共存共栄関係を築くためにも、わたしたち自身のパラダイム転換が必要になります」 |