
![INDEX[0] JFW Textile Fair 2021A/W](images/jfw_textile_fair_2021aw.jpg)
 |
![INDEX[0] JFW Textile Fair 2021A/W](images/jfw_textile_fair_2021aw.jpg) |
![INDEX[1] 開催レポート -Part 2-](images/title_index_01.gif) 日本ファッション・ウィーク推進機構(JFW)主催の「JFW JAPAN CREATION 2021(JFW-JC2021)」「Premium Textile Japan 2021Autumn/Winter(PTJ2021AW)」が11月18日~19日、東京・有楽町の東京国際フォーラム・展示ホールで開かれました。新型コロナウイルス禍の中での開催でしたが、来場者は予想以上に多く、無事閉幕いたしました。 今回は感染防止対策から出展件数・小間数とも約2割減らし、密集を避けるため通路を広げました。その結果、JFW-JCの規模は47件・242社/168.9小間(昨年は84件・294社/210.3小間)で、PTJは66件/92.75小間(昨年85件/116.5小間)となりました。 来場者数は12,626人(昨年16,811人)ですが、想定以上に多くの方が来場されました。この1年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、衣料市場は苦戦しています。テキスタイルメーカーは次シーズンの生地提案の場さえ失いかけました。それだけに「新しい商材を見たい」というバイヤーも多く見受けられ、熱心な商談会となりました。  【会 期】 2020年11月18日(水)~19日(木) 【会 場】 東京国際フォーラム 展示ホール 【主 催】 一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構 【出展者数】 JFW-JC2021:47件・242社/168.9小間(うち海外 2件・9社/5小間) PTJ2021AW:66件/92.75小間(うち海外 4件/4小間) 【入場者数】 総数12,626人(前年16,811人) JFW-JC2021、PTJ2021AWの開催レポートを2回に分けてお届けします。 Part.1(配信済み⇒記事ページへ) ・来場者の声 ・出展者の声 Part.2 ・Textile Workshop ~日本の素材を学ぼう!~ ・ピッグスキン・ファッションショー「PIGGY’S SPECIAL」 ・JFWサステイナブル・プロジェクト  ![INDEX[2] Textile Workshop ~日本の素材を学ぼう!~](images/title_index_02.gif) 動画で現場の雰囲気伝える PTJ関連プログラム「Textile Workshop~日本の素材を学ぼう!~」は、ソーシャルディスタンスを確保し、受講者数も絞って今回も開催されました。これはJFW-JC、PTJ出展の産地企業人を講師に招き、繊維業界人となって間もない(職歴5年未満)商品企画などの若手社員を対象に、寺子屋風に素材や産地への理解を深めてもらうのが目的です。2日間とも工場の現場を動画で説明され、受講者に好評でした。  初日(11月18日)は、JFWテキスタイルコーディネーター久山真弓氏と、槙田商店(山梨県郡内産地)の槙田哲也取締役工場長が登壇されました。 第1部(基礎講座)では久山氏が「日本の主な繊維産地」を紹介。「桐生産地は養蚕で盛んな着尺や帯地を生産し、日本で最初にレーヨンを使用。戦後は婦人服地としても発展し、現在もレーヨンと化合繊を主体にした複合ジャカード織物などを生産している」とし、価格帯、納期やアップチャージなどについてのアンケート結果についても説明しました。繊維の基礎知識では「織物の代表的な組織」として、平織、綾織、朱子織を解説しました。  第2部(産地レクチャー)の槙田氏は、槙田商店が絹裏地の問屋として1866年に創業し、現在は傘の製品販売、傘生地の製造、服地の製造を行っていると自社を紹介。山梨県の甲府市などのある中部から西部は「国中」と呼ばれ、葡萄や桃などを生産。日照時間が長く暖かい土地柄です。一方、東部の「郡内」は日照時間が短く寒い地域ですが、富士山の水などに恵まれて織物生産が盛んです。甲斐絹(かいき)と呼ばれる和装の裏地や座布団生地から発展し、現在はスーツの裏地、カーテン、ネクタイ、服地、夜具、座布団、ストール・マフラー、傘地などを生産しています。 今回のテーマであるジャカード織物は、織機の上で経糸を上げ下げするジャカード機械によってできます。会場では同社の工場で動くこの機械を撮影した動画を流しました。同地で有名な吉田うどんの「うどんマップ」をジャカード織で表現したものも紹介しました。ジャカードに対するドビー織機についても「柄は織れないが無地を作るのに適する。裏地や傘の無地などにも使われ、織るスピードも速い」と違いを説明しました。 郡内織物の特徴は先染細番手高密度にあります。先染は緯糸の色を混ぜて色を表現することが、プリンターの色の原理と似ています、生地の角度によって色の出方が変わり、生地の色に深みができます。高密度の織物には細い糸が必要ですが、細番手の糸は扱いが難しいといった話もされました。カットジャカード、パネル織、かせ染めについても触れました。 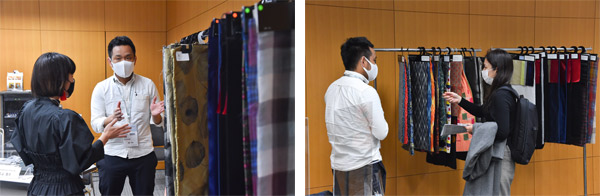 槙田氏は「産地にはかせ染め屋さんがあるが、高齢化もあって減っている。チーズ染と異なり、必要な量を染めることができるというサステイナブルな面がある。糸が膨らみ生地の目が詰まることで、チーズ染ではできない風合いや高級感が生まれる」と締めくくりました。 受講者は「動画で生産現場を見ることができた」「生産現場の話を聞けた」「海外生産しているが、新型コロナで国内を見直している。日本のさまざまな産地を知ることができ、行ってみたいと思った」と感想を述べられました。 2日目(11月19日)の第2部には中隆毛織(尾州産地)の木村正人社長が、丸編、経編の産地レクチャーを行いました。「尾州は木曽川など3河川が注ぎ、水はけのいい土壌。このため、綿花栽培を始めたのが産地の始まり。昭和初期から毛織物が盛んになり、世界を代表する毛織物産地となった。毛織物だけでなくニットも発展していった」と紹介されました。  同社は1912年創業で、綿の着尺を中心に生産。その後、毛織物に移り、73年に丸編の生産を開始しました。現在、先染のジャカード、ドビー、チェック柄を得意とし、自社工場では丸編のジャカード機や、他社にはない経糸送入機も完備しています。 木村氏はニットには丸編、経編、横編があり、丸編のシングルニットとダブルニットの違いなどを説明。持参したニット針を受講者に見せながら、ラッセル機の動画も用意して工場の雰囲気を伝えました。 「新型コロナで暗い雰囲気になり、産地では高齢化が進んでいる。しかし、若手の経営者が事業を引き継いでいる工場もあり、新しい様々な取り組みが進んでいる。かつて“触ってごらんウールだよ”というCMがあった。GoTo尾州。ぜひ産地を訪問してほしい。ほしいもの、作りたいものを産地企業に言ってほしい」とまとめました。 受講者は「ニット針を初めて見た。工場の生の話はためになる」「カットソーを扱うが、工場に行ったことはなかった。動画を見ていつか行きたいと思った」とコメントしました。木村氏はセミナー後、「尾州のニットは付加価値の高いものと期待されている。しかし、自分たちだけの考えでは売れるものはできない。消費者に近いところのニーズを聞かせてほしい」と語っていました。  ![INDEX[3] ピッグスキン・ファッションショー PIGGY’S SPECIAL](images/title_index_03.gif) 東京産地も魅力 東京都・東京製革業産地振興協議会主催のピッグスキン・ファッションショー「PIGGY’S SPECIAL」が11月19日午後、東京国際フォーラムホールのロビーギャラリーの特設ステージで開催されました。ピッグスキンは食肉の副産物として生産され、国内で唯一自給できる素材。ソフトな革、スエード、非クロム、各種仕上げ方法など技術開発も進んでいます。今回は11校の学生のほか、プロ部門として「NAPE_(ネイプ)」の山下達磨氏、「MICHAIL GKINIS AOYAMA(ミハイルギニスアオヤマ)」のミハイルギニス氏、「CHONO(チョノ)」の中園わたる氏の3デザイナーがピッグスキンを使ったショーを行いました。  山下氏は「世界主義」をテーマにしました。「豚革の独特なハリコシと非常に鮮やかな発色、安価であるゆえの汎用性の高さが魅力」と、昨年に続いての参加です。「染色技術によって表情が全く変わることがわかったので、そこをより深く理解した表現を追求」されました。 ギリシャ出身、ロンドンで服飾技術を学んだミハイルギニス氏がピッグスキンと出会ったのは10年前のPIGGY’S SPECIAL。「ピッグスキンは通気性がよく、軽く、薄い。しかも様々な加工方法があり、その組み合わせに欧州のセンスを生かすことができる」と、ストールにピッグスキンを取り入れています。 今回は「一人一人の個性」に着目し、手作業での加工や機械的な加工などを施しました。デジタルパンチング、グラデーション染め、手作業によるプリーツ、ハンドペイントやインクジェットプリントなどを組み合わせました。 中園氏は「ノーブル」をテーマに、「いかにエレガントに仕上げられるかを意識」しました。ドレープやディテールなどフェミニンな要素を取り入れました。「ピッグスキンで気になる毛穴やしぼをインクジェットプリントで隠しつつ華やかに仕上げ」ました。 レザーアイテムはほぼ初めてでしたが、工場の現場も訪れ、「素材開発においてデザイナーの意図を感じてもらえた。東京産地というのも魅力」と感想を述べられました。
![INDEX[4] JFWサステイナブル・プロジェクト](images/title_index_04.gif) 次回も継続していきます 今回から「JFWサステイナブル・プロジェクト」がスタートしました。JFWは持続可能な社会と地球環境の保全を実現していくため、サステイナブル・テキスタイルの啓発と促進に取り組んでいます。会場のトレンドコーナー「慣わしの美」にサステイナブル・テキスタイルを集めました。 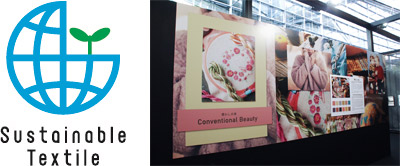 サステイナブル・テキスタイルを分類するため、大きく3分類(原料・製造工程・企業認証)し、その中に7つの詳細分類を設定しました。トレンドコーナーの該当素材にサステイナブル・カードを添付し、インデックス展示素材やブース内の該当素材にはサステイナブル・アイコンのシールを表示しました。トレンド・インデックスコーナーの737点のうち、224点(30%)がサステイナブル素材。PTJ出展者の47%がサステイナブル・アイコンを表示しました。 トレンドコーナーのサステイナブル・テキスタイルを分類すると、オーガニック原料30件、リサイクル原料28件、バイオベース原料16件、アニマルケア原料6件、製造工程21件、非有害化学物質7件、企業認証10件でした。
![INDEX[5] 2021年 JFWテキスタイル事業スケジュール](images/title_index_05.gif) Premium Textile Japan 2022 Spring/Summer 
JFW JAPAN CREATION 2022 
|
|||||||||||||||||||||||
|
||