![INDEX[1]JFW-JC2011Autumn/Winter 出展者揃う!](images/title_index_01_web.gif) |

10月13日〜15日開催のJFW-JC2011AWの出展者が揃いました。175件300小間(7月28日現在)、うち新規・復活出展者は33件32小間。また今回は海外4カ国から5社が出展します。
各種プログラムも企画進行中です。詳細が決まりましたら順次お知らせいたします。なお、「BEST of TA・KU・MI」は今回開催の予定はありません。
JFW JAPAN CREATION 2011Autumn/Winter
2010年10月13日(水)〜15日(金)10:00〜18:00(最終日のみ17:00)
東京ビッグサイト西ホール
※8月2日より、事前割引入場登録の受付を開始いたします。
出展者一覧
|
|
![INDEX[2]Tex-Promotion“FORM PRESENTION”審査会で8グループを選出](images/title_index_02_web.gif) |
繊維産地と学生のコラボレーションTex-Promotion“FORM PRESENTION”の審査会が今月15−16日に開かれ、8グループが選ばれました。今回は、JFWジャパン・クリエーションと繊維ファッション産学協議会の共催で、テーマは「デニムの加工表現」。先日行われたデニム大学を聴講した学生のうち、40グループが応募しました。
審査内容は、これまでと同じように「テキスタイルの新規性、テキスタイルと作品の適合性、作品表現の独創性、作品のリピート性、作品の完成度」の5項目。専門家による審査の結果、次のグループ(学校)が選ばれました。
これらグループは、7月26日に行われた産地見学会(カイハラほか=広島・岡山)に参加した後、加工企業とのコラボレーションによって独自のテキスタイルを作成し、アパレルやファッショングッズを製作します。その後、作品は10月13日から15日に開催されるJFW-JC2011A/Wの会場でブース展示されます。
【選ばれたテーマ/グループ名/学校名】(順不同)
protect denim/metamorphosis/(武蔵野美術大学)
Nude Color×Mou風を纏うデニム/ANNEN/(目白ファッション&アートカレッジ)
Bijou DENIM/pre pre nuit/(エスモードジャポン東京校)
Blockicy Blue/UNU/(文化服装学院)
Snail/なめくじソルトと百日咳/(文化女子大学)
Jeanne d’Arc/la Pucelle/(ドレスメーカー学院)
「人体」-The human body/1.aST/(東京モード学園)
光と影/woodruffkey/(文化服装学院広島校)
|

|
![INDEX[3]Sanchiの風](images/title_index_03_web.gif) |
 |
| 熱い想いを織り込む |
全国の産地の規模はピーク時に比べ、どのくらい減ったのでしょうか。日本絹人繊織物工業組合連合会は日本絹人繊織物工業会傘下の39産地と合わせて、約50組合の実態調査を6月から開始しました。日絹連スタッフが各産地を回って直接ヒアリングするものです。。
作業は順調に進み、7月中には調査が終わる予定です。日絹連・西紀幸理事長は調査の前に「ピーク時の10分の1の規模に縮小した産地もある」と指摘していましたが、調査の中間段階でもその印象は拭えないようです。
産地が一番困っていることは、需要の減退です。また、実際の用途でも、これまで衣料向けが中心だった産地が、非衣料分野へと移行しているところもあるようです。
生産面でも、織機が故障した場合、部品の手当てができないといった深刻なケースも。壊れた織機でもスクラップをせずに残しておいて、その部品を使うといった対応をとらざるをえない企業もあります。
言葉ではIT化を進めて革新的産業になれ!と言えます。しかし、現実とのギャップ、足元の不安定な状況は待ったなしのところにきています。そうした現実を見据えながらも、シーズンごとに新しい商品を開発している様々な産地。「JFW-JC」に出品されている何気ない生地一枚にも、そうした企業のモノ作りへの想いが織り込まれているのではないでしょうか。 |
|
![INDEX[4]グリーン&グリーン](images/title_index_04_web.gif) |
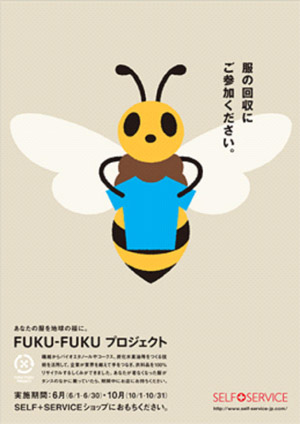 |
| 「FUKU‐FUKUプロジェクト」のポスター |
このところ繊維3R、とくにアパレルの不用品回収が活発になってきました。小売業をはじめアパレル企業でも取り組む企業が増えています。そうしたなか、昨年はテスト的に行われた「FUKU‐FUKUプロジェクト」が本格的にスタートしました。この事務局となるのがコットンをバイオエタノールにする技術をもつ日本環境設計です。
このプロジェクトに参加するのは、良品計画、イオンリテールSELF+SERVICE事業部、エドウイン、丸井グループ、アメリカ屋、らでぃっしゅぼーやの6社。消費者が店頭などに持ち込んだ衣料品を回収し、回収されたアパレルはバイオエタノールやコークス、炭化水素油などにリサイクルされます。
不用品をエタノールなどにリサイクルする状況について日本環境設計の岩元美智彦社長は「ゴミの再生は、いわば都市資源の開発」と話していますが、繊維のゴミが貴重な資源として用いられたのは明治時代にさかのぼるようです。
故繊維業界の大手、ナカノの窪田恭史氏(リサイクル部事業企画室長)によると、ボロ、すなわち使用済みのアパレルやテキスタイルは、江戸時代に売買されていました。そしてボロが事業として成立するようになったのが明治以降で、最初の需要は製紙工業だったようです。窪田氏はHP(http://www.nakano-inter.co.jp/)で、そのあたりを次のように記しています。
「明治初年に日本に初めて設立された製紙工場は木綿や麻のボロを製紙に使いました。したがって、当初の製紙工場はボロを集めやすい東京や京阪神に集中していました。やがて、わらパルプの混用が始まると、製紙工場は地方に移転し始め、明治22年には、最初の国産木材パルプ工場が静岡県に建設されます。それでも明治36年ごろの資料によれば、ボロパルプは全体の20.5%を占めていたようです」
つまり、繊維製品はかつても貴重な都市資源だった、ということになります。100年以上の月日を経て、再び繊維ゴミが資源になるというのも“繊維リサイクル”ならではの循環といえるでしょうね。
|
|
| |
|
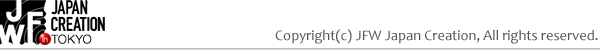 |
![JFW JAPAN CREATION [Mail Magazine] 一般社団法人日本ファッションウィーク推進機構 JFWジャパン・クリエーション http://www.japancreation.com/](images/title_top_01_600.jpg)


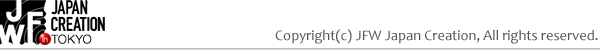
![JFW JAPAN CREATION [Mail Magazine] 一般社団法人日本ファッションウィーク推進機構 JFWジャパン・クリエーション http://www.japancreation.com/](images/title_top_01_600.jpg)